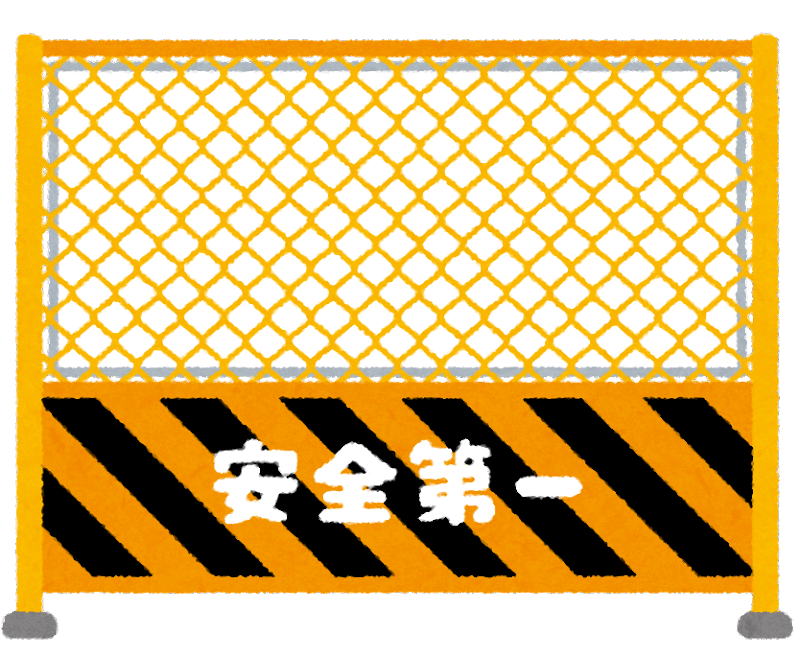建設業の安全大会では、講演会をするならどんな講師を呼ぶべきなのか?
「安全大会では、どのような外部講師を招いて講話をしてもらうべきか?」と考えている社長やご担当者は多くいらっしゃるのではないでしょうか。この記事の前半では「建設業の安全大会の基本」、そして後半では「建設業の安全大会の講師選びの考え方」を、わかりやすく解説していきます。
建設業で行われる安全大会とは
安全大会の講師選びについて考える前に、「そもそも建設業の安全大会とは何か」について整理してみましょう。
建設業の各社で行われている安全大会は、毎年5〜8月に開催されるのが慣例となっています。なぜこの時期に安全大会が行われるのかというと、厚生労働省と中央労働災害防止協会が中心になって行われる「全国安全週間」が毎年7月1日〜7日に設定されているからです。
この前後の5〜8月に建設業の各社で安全大会を行うことで、全国安全週間の目的である「安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を高める狙いがあります。
なお、全国安全週間がはじまったのは昭和3年。以来、戦争中も含め一度も中断することなく続いてきた、建設業、貨物運送業、林業・木材製造業などの業界にとって重要な催しです。
全国安全週間は、下記の主唱者、協賛者、協力者、実施者が連携しながら実施しています。
| 主唱者 | 厚生労働省、中央労働災害防止協会 |
| 協賛者 | 建設業、貨物運送事業、林業・木材製造業など各業界の労働災害防止協会 |
| 協力者 | 関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 |
| 実施者 | 各事業場(建設会社など) |
参照:中央労働災害防止協会「令和4年度 全国安全週間実施要綱」
建設業の各社が安全大会を行う意味とは
建設業の各社で行われている安全大会では、次のような施策を通して「安全意識の向上と安全活動の定着」が図られています。
・経営者による安全への所信表明
・講演会を開催し、講話を聴く
・現場の安全パトロール
・安全旗や標語による決起
・緊急時の訓練
・安全関係資料の配布
・職場見学の実施 など
建設会社であれば、日頃から現場において安全の指導・啓蒙に努めているケースがほとんどでしょう。それでも、建設会社が安全大会に力を入れるべき理由は、建設業は労災の件数や死傷者数が多いからです。
たとえば、労災対象の志望者数は全産業で867人になります。そのうち、288人を建設業が占めています(2021年度)。これは全体の33%を占める、非常に高い割合といえるでしょう。
また、近年減少していた建設業の労災対象の災害が、2021年に死亡数・死傷者数ともに増加に転じているのも気になるところです(下記の表参照)。
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 死亡災害 | 269人 | 258人 | 288人 |
| 死傷災害 | 15,183人 | 14,790人 | 14,926人 |
出所:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況の分析等」より一部抜粋
*死傷災害数は新型コロナ感染による労災を除いた数
2021年の建設業の死亡災害数は前年よりも30人も増加しています。今後、作業者のさらなる高齢化などを考えると、現場での安全意識の向上は喫緊の課題といえるでしょう。
こうした背景を踏まえると、建設業の各社は「安全大会」にこれまで以上に精力的に取り組む必要があるのではないでしょうか。
安全大会の開催は建設業の各社の義務?
安全大会の開催は、建設業の会社の法的な義務ではありません。一方で、厚生労働省が建設業界向けに提示した資料では、安全衛生管理に必要な費用区分(細目)として「安全大会」を明記しています(下記参照)。
これを踏まえると、コンプライアンスの観点で建設業の各社が安全大会を行うのが望ましいといえるでしょう。
| 費用区分 | 主な内容 | 細目 |
| 現場管理費 | 安全訓練研修等に要する費用 | ・特別教育、各種資格取得のための講習受験費用 ・避難、救護、消火訓練等、送り出し教育、新規入場者教育、安全協議会、安全大会、RST、CFT |
厚生労働省「安全衛生経費確保のためのガイドブック」(制作委託:建設産業振興センター)より抜粋
建設業の安全大会で講演を必ず開催しなければならない?
次に確認したいのは、「安全大会で講演会を必ず開催しなければならないのか」ということです。
これについては、「全国安全週間実施要綱」の各実施者(建設会社)が実行すべきこととして「講演会等の開催」と明記されています。下記がその要綱の内容ですが、項目3に「講演会等の開催」とあるのが分かります。
1.安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚
2.安全パトロールによる職場の総点検の実施
3.安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
4.労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ
5.緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
6.「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施
引用:参照:中央労働災害防止協会「令和4年度 全国安全週間実施要綱」
とはいえ、国内に数ある建設会社の大半が安全週間の1週間以内に講演を行うのは困難です。便宜上、5〜8月に各社で行われる安全大会のなかで講演を行うのが現実的でしょう。
安全大会の目的や意義などについて改めて知りたい方は、下記の記事をご覧くださいませ。
建設業の安全大会では、どんな講師に依頼すべき?
では、安全大会のなかで講演を行うとした場合、どうすれば良いのでしょうか。
安全大会の講演を通じて、社員や作業員の安全意識を効果的に高めるには、やはりプロの外部講師を招くのが望ましいでしょう。だからといって「話題の講師だから」「他社でやっているから」といった何となくの理由で依頼するのは避けるべきです。
なぜなら、安全大会の講演には「安全意識の高揚と安全活動の定着」という命題があるからです。これに貢献する講演を実施するであれば、なりゆきではなく、次のような流れで外部講師を絞り込んでいくのがよいでしょう。
- 会社や現場の安全に関するテーマ(課題)を見つける
- テーマをより具体化する
- そのテーマにふさわしい外部講師をピックアップする
- 予算との擦り合わせを行う(講演の料金や交通費など)
- 事前の打ち合わせで社員や作業員に合った内容や方向性にする
講演の大きな方向性は、下記のABCの3つが挙げられます。
(A)安全意識を直接高める
(B)仕事の基本姿勢を改善する
(C)作業員の健康意識を高める
それぞれの方向性を詳しく見ていきましょう。
●安全大会の講演の方向性 A:安全意識を直接高める
建設業の安全大会の講演テーマでニーズが多いのはやはり、安全意識を直接高めるものでしょう。この方向性で講演依頼をするなら、現時点の会社や現場で意識が足りない部分、あるいは直面している問題を洗い出し、その内容について知見のある講師を招くのが得策です。
テーマ例は次の通りです。
・労災事故
・墜落・転落事故
・防災・危機管理
・転倒事故
・ヒヤリハット
・失敗学
・フルハーネス型安全帯 など
●建設業の安全大会の方向性 B:仕事の基本姿勢を改善する
「現場でのコミュニケーション」「パワハラ防止」「仕事へのモチベーション」など、社員や現場作業員の仕事に対する考え方を改善することで間接的に安全意識を高めることも可能です。
また、過去の安全大会で「安全意識を直接高める講演をやり尽くした」という企業は、変化を付ける意味でこの方向性が向いているかもしれません。
●建設業の安全大会の方向性 C:作業員の健康意識を高める
労災の原因には、過度なストレス、不眠、疲労感などが影響することも多く、健康対策に注力する建設会社も少なくありません。
最近の建設業界では「健康KY」の取り組みも広がっていますが、これと併せて、睡眠、食事、メンタルヘルス、喫煙問題など健康をテーマにした安全大会の講演を行うと効果的です。
また、とくに作業員の平均年齢の高い建設会社や現場では、メタボ、認知症、年齢と作業危険度などのテーマを設定した安全大会の講演も考えらます。
●建設業の講師依頼は、中長期的な視点で考えよう
安全大会の講演を毎年同じようなテーマで行うとマンネリ化してしまい、社員や作業員が飽きてしまいます。これを防ぐには、安全大会の講師依頼を5〜10年程度など中長期的に考えていくのが効果的です。下記は、6年単位でテーマを計画した場合の一例です。
・1年目講演テーマ:防災と危機管理
・2年目講演テーマ:現場コミュニケーション
・3年目講演テーマ:質のよい睡眠
・4年目講演テーマ:ヒヤリハット
・5年目講演テーマ:モチベーション向上
・6年目講演テーマ:食事管理
上記の例では、(A)安全意識を直接高める(B)仕事の基本姿勢を改善する(C)作業員の健康意識を高めるという3つの方向性を3年ごとに1周することで、講演のマンネリ化を防いでいます。
安全大会の講演講師なら原マサヒコへ
ここまで、建設業における安全大会について解説してきました。
安全大会の方向性やテーマがある程度固まったら、早めに講師依頼を行うようにしましょう。「どれくらい前のタイミングで講師依頼をすればよいか」については、一般的な講演では開催日の3〜4カ月前程度といわれます。
しかし、人気講師の場合はかなり早い段階でスケジュールが埋まってしまうことも少なくありません。また、安全大会で人気の講師の場合、安全週間前後の数カ月に依頼が殺到します。それらを考慮すると、早めの依頼を行った方が良いでしょう。具体的には5カ月〜6か月前に依頼するのが無難と考えられます。
もし建設業の安全大会で講師をお探しの場合、ぜひ原マサヒコにお任せ下さい。
これまで多くの建設業からご依頼があり、高い評価をいただいております。「お客様の声」を含め、詳細につきましては、下記の専用サイトをご確認のうえお気軽にお問い合わせください。
↓ ↓ ↓